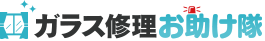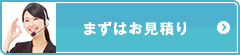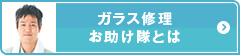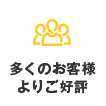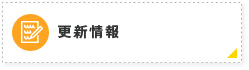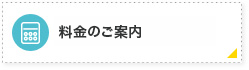“フロートガラス”というと、聞き慣れないという人が圧倒的多数でしょう。しかし実は、フロートガラスは私たちの暮らしに非常に身近な存在です。といわれても、すぐにピンとこない人が多いでしょう。フロートガラスは一般的にいわれるガラス、そのものを指します。
日本でもっとも普及しているガラスが、フロートガラスといっても過言ではないでしょう。昔から長いあいだ使用されてきたフロートガラス、その存在は私たちの普段の暮らしに欠かせない存在です。フロートガラスは、さまざまなガラスの元にもなっています。
“普通のガラス”、フロートガラスの特徴とはなんなのでしょうか?灯台もと暗し、身近過ぎるものほど、その情報については詳しくないことが多いでしょう。あなたの持つその疑問、当コラムがすべて解消します。フロートガラスの永久保存版、ぜひ最後までご覧ください。
フロートガラスとは
“ガラス”といっても、その中にはいくつもの種類が存在しています。強化ガラスや防音ガラス、断熱ガラスなど、その種類もさまざまです。その種類の中のひとつである“フロートガラス”、その具体的な正体とは、一体どのようなものなのでしょうか?
いわゆる「ふつうのガラス」です
フロートガラスは、私たちが日常的に目にするガラスのなかでも、もっとも一般的な存在です。フロートガラスはまったくの透明ではなく、厚みがあったり、重ねたりすると鮮やかな緑色を発色するようになります。なんだか景色が緑に見える原因は、このガラスです。
純度の高い、まったくの透きとおったガラスは“高透過ガラス”と呼ばれています。緑をたたえるフロートガラスとは、透明度が異なるのです。フロートガラスの特徴は詳しく後述しますが、加工のしやすさや、厚みの種類が豊富なことが、大きなものといえます。
こんな場所に使われています
一般的、といわれるくらいです。フロートガラスが使用されている場所は、非常に多岐(たき)に渡ります。窓ガラスへの使用はもちろん、ガラス製のテーブルや棚板や扉にまで、その使用用途は多種多様です。日常的に目にする機会も多いでしょう。
また、フロートガラスは厚みが増すと強度も上がります。その代表例が、熱帯魚などを泳がせるための“水槽”への利用ではないでしょうか。大量の水を注ぐため、使用するガラスに強度は必須です。水槽に使用されるフロートガラスの強度は、抜群といえるでしょう。
フロートガラスの歴史

ガラスの中でも、もっとも普及しているといわれているフロートガラス。その歴史の始まりは、1952年にまで遡(さかのぼ)ります。フロートガラスが開発されたのはイギリス。溶かしたガラスの溶液を、熱した錫(すず)の上に浮かべることで、完成しました。
それ以前のガラスは表面の凹凸がひどく、ガラスをとおして見えた景色は歪んだものになったといわれます。その症状を見事に解消したフロートガラス。その開発は、ガラス業界を大きく変えたことでしょう。現在でもガラスの多くは同様の手法で作られています。
フロートガラスを使用するメリット
大きく普及しているフロートガラス。その背景には、フロートガラスの持つさまざまなメリットが存在しています。一般的なガラスともいわれるフロートガラスですが、ほかのガラスにはない、いろいろな個性も持ち合わせているのです。詳しく紹介しましょう。
厚みの規格が10種類もあり豊富
フロートガラスは、ガラスの基礎になるものです。そのため、選べる種類、とりわけ厚みに関しては選択肢が非常に豊富です。代表的な10種類の厚みは、下記のようなものです。
- 2mm
- 3mm
- 4mm
- 5mm
- 6mm
- 8mm
- 10mm
- 12mm
- 15mm
- 19mm
これだけの厚みの選択肢を持つガラスは、ほかにないでしょう。とりわけ、フロートガラスは厚みによって印象や雰囲気が大きく変わります。窓ガラスであれば、景色の見えかたにも、大きく影響を及ぼします。透明度や頑丈さで選ぶことも、可能になるでしょう。
加工しやすく、価格も安い
フロートガラスは加工しやすく、かつ価格が安いことも大きなメリットでしょう。好みの大きさに切りわけたり、穴を空けたりすることも容易です。DIYなどで、自分で加工をすることも難しくはないでしょう。変わった形にすることも、できるかと思います。
また、フロートガラスは流通している量が多いため、ほかのガラスよりも安い価格で入手することができるでしょう。加工のしやすさも相まって、非常に使い勝手がよいガラスといえます。フロートガラスが広まった背景には、価格設定の安さの影響も大きいでしょう。
対応業者が多い
1952年に開発されたフロートガラス、その歴史の長さから、対応できるガラス業者の数が多いということもメリットでしょう。フロートガラスは、多くのガラスを扱う業者に常備されており、修理や交換の要望に対しても、ほとんどの業者が対応することが可能です。
ガラストラブルの大多数を占めるであろうヒビや割れなどに対応できる業者が多いということは、トラブルの解決も容易なことを意味します。迅速な作業も期待できるでしょう。
デメリットは、高機能ではないこと
多くのメリットが存在しているフロートガラス。一般的とはいうけれど、多くの個性を持ち合わせていますよね。反面、フロートガラスが持つデメリット。それは“高機能ではないこと”です。よくも悪くも、フロートガラスは一般的なガラスなのです。
たとえば、強度の面では強化ガラスに軍配が上がるでしょう。防音の面では防音ガラスに、断熱の面では断熱ガラスが圧勝します。フロートガラスの使い勝手は抜群ですが、新しいガラスに比べると、追加の機能がなく性能面ではどうしても劣ってしまうのです。
フロートガラスには上記のように多くのメリットと、少ないデメリットが備(そな)わっています。歴史が証明しているように、フロートガラスの信頼性は確かなもの。一般的といわれる理由は、ここにもあります。必要十分な機能を持ったガラスの代表例でしょう。
フロートガラスの耐用年数は数十年と長い

こちらも同様に、フロートガラスのメリットともいえるかもしれません。フロートガラスの耐用年数の目安となるのはなんと20年以上。中には「40年以上の使用を続けてもいまだに現役」という声もあるほどです。およそ半世紀ほどの耐用度、圧巻といえるでしょう。
手入れを欠かさずおこなえば、非常に長い期間を共に過ごすこともできるでしょう。家の外壁塗装や屋根の張り替えなど、代表的な家の建具は定期的なお手入れが欠かせません。その点フロートガラスの長寿命は、家の維持費を考えるうえでも有益といえます。
フロートガラスの耐熱温度は100度強!
ガラスというと、熱に弱い印象があるという人も多いでしょう。しかし、その印象はフロートガラスには当てはまりません。フロートガラスの耐熱温度はなんと100℃、熱湯を不意にかけてしまっても、割れる心配はないのです。この特徴は意外だったでしょうか?
とはいえ、例外はあります。それはガラスと熱のあいだに、大きな温度差が生じたときです。たとえば、熱したガラスを急激に冷やしたり、冷たいガラスに熱湯をかけてしまった場合は、パリンと割れてしまうことがあるのです。温度差には弱いといえるでしょう。
ちなみに、熱に強いといわれている強化ガラスの耐熱温度はおよそ210℃、この点強化ガラスは優秀でしょう。とはいえ、加工がしやすく価格も安い、さまざまなメリットがあるフロートガラスの耐熱性としては十分でしょう。需要(じゅよう)を満たす機能といえます。
フロートガラスは最大どのサイズまで作れるのか
さまざまに輝くメリットが光るフロートガラス、その存在は無視できません。そして、ここからの情報も非常に有益なものです。フロートガラスで作れる最大のサイズ、気になるのではないでしょうか?加工ができても大きさが足りなければ、意味がありませんよね。
フロートガラスの最大寸法は、およそ2,000mm×3,000mmです。この最大のサイズを基準に、それぞれの用途に合わせたサイズにガラスを加工、状態をアレンジしていきます。業者に依頼をすれば、自分好みのオリジナルサイズに処理してもらうことも可能でしょう。
そのとき気になるのが、フロートガラスの加工をはじめ、修理や交換にかかる費用ではないでしょうか?自分だけの好きなサイズに加工をしてもらうほか、窓ガラスが割れたり、棚のガラス板にヒビが入ってしまったりすることもあるでしょう。
そんなときに依頼する業者選び、価格が安いとはいえ、少しでも安く抑えたいというのが人情でしょう。そんなときは、インターネット上にある比較サイトを使用してみてください。いくつかの業者が提示する作業の費用を簡単に比較、検討することができます。
また、具体的な業者選びをするのであれば、業者の公式サイトやクチコミサイトを参照してみることも、非常にお役に立つでしょう。公式サイトでは業者のこれまでの実績や事例の確認を、クチコミサイトでは作業を依頼した人の“生の声”を知ることができます。
フロートガラスの魅力を最大限に発揮させるのであれば、依頼する業者選びも重要な要素でしょう。せっかくなら信頼のおける業者に作業を依頼したいところ。ぜひこの章の情報を参考にして、信頼のおける素晴らしい業者を、探し出してみてください。
まとめ
もっとも一般的なガラスといわれるフロートガラス、その正体は私たちの暮らしにとても身近なものでした。今現在フロートガラスを自宅で使用している、という人も多いでしょう。日常的に目にするガラスの中にも、フロートガラスは多く存在しています。
1952年に開発されてから、多くの場所で使用され続けているフロートガラスは、その信頼性も抜群でしょう。使用されている歴史が長いということは、それだけ知識の積み重ねがあり、対応できる業者の数も多いといえます。修理や交換のときも、対処は容易でしょう。
厚みのバリエーションも多く、加工がしやすい、価格も安いなど、多くの面でメリットを持つフロートガラス。これからご自宅に導入しようという人は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?新しいガラスにはかないませんが、必要十分な機能を持ち合わせています。
耐用年数の長さ、耐熱温度の高さは、目を見張る事実でしょう。最大寸法も十分に大きなものといえ、加工を依頼するにも問題ありません。お好みに合わせたガラスの姿を実現するために、フロートガラスは多くの選択肢をあなたに与えてくれます。
ガラスの加工はもちろんのこと、修理や交換を業者に依頼するのであれば、簡単にできる費用見積りをおこなってみるのがよいでしょう。信頼できる業者を探し出すことができます。身近なところにあるフロートガラス、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか?

新しい家に越してきたら周囲の騒音が気になるという人や、自宅の周りの環境が変化して騒音が気になるようになったという人もいるでしょう。騒音でお悩みであれば、防音対策をすることがおすすめです。とくに窓ガラスは騒音が侵入しやすい場所なので、窓ガラスの防音対策はとても効果的です。
このコラムでは、窓ガラスの防音対策の方法について解説していきます。防音対策にはさまざまな方法があるので、ご自身の環境にあった方法を選んでみてください。
防音のカギは窓にある!
窓ガラスの防音対策について解説する前に、まずはなぜ窓ガラスから騒音が伝わりやすいのかをご説明します。窓ガラスは音を伝えやすい構造をしているため、防音対策するときは、まず窓から対策するとよいでしょう。
窓は壁に比べて薄い

住宅の壁は、さまざまな壁材でつくられていますが、すべて合わせると厚さがおおよそ155mm程あるとされています。それに比べて、基本的な窓ガラスの厚さは3~5mmと大変薄いです。
そのため窓がない部屋よりも、窓がある部屋の方が、騒音が伝わりやすくなってしまうのです。窓がない部屋なら静かに感じるような音でも、窓ガラスがある部屋では、でうるさく感じてしまうほど、聞こえ方にも違いがあります。
現在、複層ガラスとよばれるものを、窓ガラスに使用しているお宅もあります。この複層ガラスは2枚のガラスを使用し、間に空気またはガスの層ができたものです。このガラスは断熱効果や結露防止に効果があるようですが、防音には効果はありません。ガラスを2枚使用している分、防音効果もありそうですが、通常のガラスとさほど変わりません。
その理由は、音は空気の振動で伝わるからです。複層ガラスの2枚のガラスは同じ厚さでできているので、2枚とも同じように振動します。そのため、音を小さくすることができないのです。
窓とサッシの間にはすきまがある
窓ガラスから音が侵入しやすい原因には、ガラスの厚さ以外にも理由があります。それは窓ガラスにはサッシがあることです。
サッシは窓ガラスの開閉をスムーズにおこなうために、すきまが空いています。そのすきまを通って、音が侵入してくるのです。しかも、サッシは1mm程度のアルミを使ってつくられているので、簡単に音を通してしまいます。このようなことから、窓ガラスは音を伝達しやすい場所となっているのです。
【窓の防音1】しっかり対策編
いよいよ、窓ガラスの防音対策について解説していきます。しっかりと防音したいのであれば、やはり業者に相談するのが一番でしょう。
防音ガラスに交換する

防音ガラスは、2枚以上のガラスでできています。そう聞くと複層ガラスのようですが、ガラスとガラスの間に特殊中間膜というものを挟んでいます。(防音ガラスを使用した複層ガラスもあります)
この特殊中間膜は振動を熱に置き換え、音の波を消滅させる効果があります。どの音域にも効果があるため、防音性が高いです。サッシにも防音タイプがあり、これとあわせて使うとさらに効果的です。
二重窓(二重サッシ・内窓)にする
既存の窓をそのままに、内側にもうひとつ窓を取り付けることによって二重窓にする方法もあります。既存の窓と、内側に取り付けた窓との間で音が反復するため、部屋の中にまで音が伝わりにくくなります。既存の窓をそのまま使うので、おおがかりな工事はいりません。
ただし、窓のタイプや、内側にもうひとつの窓を取り付けるスペースがあるかどうかで、施工方法が変わってきます。また、内側に取り付ける窓ガラスの防音性によって、効果に差が出てきます。そのため、防音性の高いガラスを選ぶことが大切です。
二重窓には防音効果以外にも、うれしい効果があります。それは断熱効果が高いことです。断熱効果が高いということは、夏は室内を涼しく保ち、冬は室内を暖かく保つことができるということです。また、その効果により、結露を抑えることもできます。まさに、よいことだらけの窓といえます。
ガラスの交換、二重窓の設置は自分でできる?
防音ガラスへの交換や二重窓の設置を、自分でできないかとお考えの人もいることでしょう。自分でできれば費用も抑えられるため、うれしいところです。しかし、これらの作業を素人がおこなうのは大変難しいです。
施工には家の構造をよく把握し、家屋の歪みに合わせた部材を用意しなければなりません。適切に施工できないと、窓の脱落がおこり、ガラスの破損、怪我などにつながりかねません。防音ガラスへの交換や、二重窓の設置は、必ず業者に依頼して施工してもらいましょう。
【窓の防音2】おてがる対策編
防音にかける費用を抑えたい、おおがかりな施工はしたくないという人もいるでしょう。ここでは自分でできる、簡単な窓ガラスの防音方法をご紹介していきます。
窓とサッシの隙間をふさぐ

窓とサッシにできるすきまを、テープを使ってふさいで、防音することができます。このときに使うテープは防音テープ・遮音テープ・すきまテープなどさまざまな名前でよばれています。好きな長さにカットして貼り付けるだけなので、作業も簡単です。
しかし、テープですきまをふさぐだけでは、あまり防音効果は感じられないかもしれません。ほかの方法と併用して使うとよいでしょう。また、テープは経年劣化してボロボロになってしまうので、定期的に交換も必要です。
防音シートを張る
防音シートは、ガラスに貼って使用します。厚みがあるほど、防音効果は高いです。しかし、厚みがあるとそのぶん取り扱いが難しくなるので、どれくらいの防音効果が必要かなどによってシートを選ぶとよいでしょう。
このシートは、簡単に剥がすことができるので、賃貸などでも使いやすいでしょう。また、窓ガラスにシートを貼り付けると、結露を防ぐ効果もあります。貼るときは、すきまができないよう少し大きめにカットしてから貼るとよいでしょう。
防音カーテンに変えてみる
防音カーテンはさまざまなタイプのものがあります。
- 樹脂コーティングしたもの
- 金属をコーティングしたもの
- 吸音効果がある特殊な織り方でできたもの
- 生地を複層にしたもの
またこれらを併用してつくられた防音カーテンもあります。防音カーテンを設置するときは、窓からの音が伝わらないように、しっかりと窓をカバーするサイズのものを選びましょう。
ただし、防音カーテンは低音には効果があまりないです。そのため、工事の音や車・電車の音などは、防ぐのが難しいでしょう。
簡単にできる対策では効果が感じられないときは
このように、自分でも簡単にできる防音対策もありますが、やはり防音ガラスや二重窓に比べると効果が落ちてしまいます。自分でできる方法を試してみて、それでも騒音が気になるときは、ぜひ業者に相談してみてください。弊社では、お客様のご相談に合わせて業者をご紹介しています。お悩みのことがあれば、一度相談窓口までご連絡ください。

ガラスにできた傷は、傷の度合いによって対処方法が異なります。小さな傷であれば自分で対処することも可能ですが、大きなガラス傷は早めに業者へガラス交換を依頼することをおすすめします。
このコラムでは、小さなガラス傷の対処方法とガラス交換の費用相場について解説していきます。ガラスの傷でお悩みの際は、参考にしてみてください。
小さい傷の補修方法
基本的に「ガラスの表面の引っかき傷/スリ傷」や「ガラスの表面の軽い欠損」などの小さいガラスの傷は、直すことこそできませんが目立たなくすることは可能です。ここでは、ガラスについた小さい傷を目立たなくする方法について解説していきます。
研磨する方法

研磨剤を使用してガラスの表面を磨く方法です。窓ガラスや車のフロントガラスなどについた小さな傷を目立たなくさせることができます。
しかし、力加減を間違えると余計にガラスの傷が増えたり、ガラスが割れたりなどのトラブルの発展するケースがあるため注意が必要です。ガラスの研磨には以下のようなものが利用できます。
【市販の研磨剤】
「ガラスの傷消し」やガラスの傷修復」として販売されているガラス用の研磨剤です。使用方法は、付属の説明書を確認してみてください。
【酸化セリウム粉末】
ガラスを磨く際に、とくに効果的な研磨剤は「酸化セリウム」という物質です。この物質はガラスと特殊な化学反応を引き起こして傷をなめらかに仕上げてくれるので、ガラス研磨との相性がとくによいとされています。このことから、市販のガラス研磨剤に含まれていることが多い物質です。酸化セリウム粉末で窓ガラスを研磨する方法は以下のとおりです。
- 傷がついた場所を軽く拭き取り、表面についているホコリやゴミを取り除く。
- 容器を用意し、その中で酸化セリウム粉末と水を軽く混ぜ合わせる。
- 酸化セリウム粉末と水を混ぜ合わせたものを研磨する場所にかける。
- 柔らかい布やスポンジなどでガラスをこする。
【重曹】
重曹は粒子が細かく水に溶けないため、ガラスの研磨剤として利用できます。使い方は酸化セリウム粉末と同じで、水と混ぜて傷を布などでガラスの表面をこすれば研磨できます。
【歯みがき粉】
歯磨き粉には歯についた汚れを落とすための研磨剤が含まれているため、ガラス磨きに応用することが可能です。しかし、歯周病や知覚過敏向けの歯みがき粉などには研磨剤が含まれていないケースもあるため注意が必要です。傷に歯みがき粉を塗りつけ、布などでこすってガラスを研磨しましょう。
傷を埋める方法
市販の補修液で傷を埋める方法です。おもに、車のフロントガラスの表面にできた欠損に対応できます。補修液は通販サイトやホームセンターなどで「ガラスリペアツール」「ガラス補修キット」として販売されていることが多いです。使用方法は製品ごとに若干異なるため、説明書を熟読した上で利用するようにしましょう。
大きな傷はガラス交換を
「ヒビが入った」「ガラスが欠けて穴ができた」などの大きなガラスの傷ができた場合は、無理に手を加えずにできるだけ早く業者へ修理または交換を依頼することをおすすめします。
しかし、時間がないなどの事情ですぐにはガラスの修理や交換ができないというケースもあるかもしれません。そこで、ここでは大きなガラス傷ができた際の応急処置方法を解説します。
大きな傷の応急処置方法

大きな傷の入ったガラスは、そのままにしておくと傷が広がって割れてしまう危険性があります。そのため、ガラスの傷がこれ以上広がらないような処置が重要になってきます。
傷が広がるのを防ぐのに有効なのが「補修テープ」です。ガラスの傷に貼り付けることによって、傷が広がるのを防ぐことができます。また、万が一ガラスが割れた際に、ガラス片が飛び散らないようにしケガを予防する効果もあります。テープを貼りつける際は力を掛け過ぎてガラスを割ってしまわないように意識しましょう。
補修テープがない場合は、ガムテープで代用可能です。しかし、ガムテープは防水性能があまり高くなく、ガラス傷から雨水などが侵入してくる可能性があるので、可能な限り補修テープを用意することをおすすめします。
ガラス交換の費用相場について
大きなガラス傷ができている場合はそのまま放置しようとせずに、早めにガラス交換をおこなうことをおすすめします。ここでは、車のフロントガラスと窓ガラスの交換費用の相場について紹介していきます。
車のフロントガラスの交換費用相場

車のフロントガラス交換にかかる費用はおもに「車種」「交換するガラスの種類」によって左右されますが、5~10万円が相場になってきます。
ガラスの種類は大きく分けると、メーカーが作っている「純正品」と二次メーカーで作っている「社外品」があり、基本的に後者のほうが若干安いです。そのため、交換費用がどうしても高いと感じる場合は、社外品のガラスに交換するのもひとつの手です。
また、翌年の保険等級が下がるというマイナス点こそありますが、自動車保険を利用してフロントガラスの交換費用を補填してもらうこともできます。
家の窓ガラスの交換費用相場
窓ガラスの交換にかかる費用はおもに「窓の種類」「窓のサイズ」によって変動します。窓ガラスの種類はたくさんあるため、ここではその中でも一般的なマンションで使われていることが多いものを紹介していきます。
【フロートガラス/透明ガラス】
とくに特殊な加工が施されていなく、価格の安いガラスです。
【網入りガラス】
中にワイヤーが埋め込まれていて、万が一割れた際に破片が飛び散りにくいガラスです。
【型板ガラス/かすみガラス】
表面に凹凸があり、外から中を見通せないという目隠し機能があるガラスです。
窓ガラスのサイズは900×900mm前後/900×1200mm/900×1800mm前後で分けられていることが多く、それぞれ値段が異なります。ガラス業者数社の窓ガラス交換の費用相場についてまとめたので、業者に依頼する際の参考にしてみてください。
【大きさ900×900mm前後】
透明ガラス(厚さ2mm) 約6,000~12,000円
型版ガラス(厚さ2mm) 約10,000~18,000円
網入りガラス(厚さ6.8mm) 約20,000~35000円
【大きさ900×1200mm前後】
透明ガラス(厚さ3mm) 約9,000~20,000円
型版ガラス(厚さ4mm) 約12,000~20,000円
網入りガラス(厚さ6.8mm) 約30,000~33,000円
【大きさ900×1800mm前後】
透明ガラス(厚さ3mm) 約13,000~23,000円
型版ガラス(厚さ4mm) 約14,000~23,000円
網入りガラス(厚さ6.8mm) 約36,000~42,000円
ガラス交換の費用は業者ごとに大きな差が出るケースがあるため、正確な料金を知るのは難しいです。そのため、なるべく交換作業をする前に見積り出してくれる業者を選ぶことをおすすめします。
弊社では、ご自宅の窓ガラスや車のフロントガラスの修理・交換ができる業者をご紹介しています。また、相見積りもおこなえ、施工前であればキャンセル料も不要なため安心してご利用頂けます。相談窓口は無料かつ24時間365日いつでもご利用できるため、ガラスの傷でお困りの際はお気軽にお電話ください。

強化ガラスは、割れにくく飛び散りにくいという性質を持ちます。そのため、小さなお子さまがいるご家庭や台風などの影響を受けやすい地域にお住まいの方など、さまざまな用途で設置されます。
しかし、強化ガラスは窓ガラスとしてよく使われるフロートガラスより、価格は高めの設定となってしまいます。交換を検討する際には、あらかじめ強化ガラスの値段の確認をしておきましょう。
強化ガラスは、厚みや大きさによって費用は大きく変動します。このコラムでは、強化ガラスの値段と交換費用の相場を解説しています。自分で交換したい方に向けてDIYの方法もご紹介していますので、業者に依頼したい方、DIYしたい方それぞれ参考にしてみてください。
強化ガラスの値段と交換したときの費用相場
強化ガラスは、機能性によって値段が異なります。はじめに、そのなかでもよくご家庭で設置されることのある種類の費用相場や、交換する際に知りたい情報を解説していきます。
強化ガラスの値段は大体いくら?

強化ガラスは、ほかのガラスと同じように厚さによって値段が異なります。5ミリメートルから19ミリメートルとさまざまな厚さの強化ガラスがあり、より厚いほど値段が高くなる傾向があるのです。
窓ガラスとして使用される強化ガラスは、基本的に5ミリメートルほどの厚さのものが多いです。この厚さであれば、900ミリメートル×800ミリメートルのサイズの窓ガラスでは、相場は20,000円~30,000円ほどです。同じ大きさでも、厚さが10ミリメートルともなれば、30,000円~40,000円ほどまで相場も値上がりします。
強化ガラスへ交換したときの費用相場
業者にガラス交換を依頼する際には、ガラス代とは別に作業費として、10,000円~15,000円ほどがかかります。さらに、元から設置してあった窓ガラスの処分代や出張費がかかる業者もあります。
ガラスは厚みがあるほど丈夫であるため、より効果的な強化ガラスを設置するには、元のガラスよりも厚みが必要です。もし厚みを変える場合は、窓枠やサッシの交換をすることになり、取り換えの費用相場は100,000円ほどとなります。ただし、窓の大きさによっても費用は異なりますので、具体的な費用が知りたいときには業者に見積りをとってもらいましょう。
強化ガラスへの交換はどれくらい時間かかる?
強化ガラスは特殊なガラスとなり、業者に在庫がなく、取り寄せとなる場合があります。取り寄せの場合には、およそ1週間かかるため、交換を考えている場合にはあらかじめ業者に連絡しておくとスムーズです。
ガラスの設置自体は、サイズの確認ができていれば1時間弱ほどで交換ができます。もしも、ガラスが割れたというケースなどではやく交換がしたいという場合には、複数のガラス業者に在庫の確認をすることや、もしくは交換までガラス業者に応急処置をしてもらうこともできますので、相談してみてください。
窓枠やサッシの交換をする場合には、工事に1日~3日ほどかかります。ただし、状態の確認をして必要な作業を見積もる必要があることから、交換を決めてから最短でも1週間ほどかかることがあります。
ガラス業者に交換を依頼したときの流れ
ガラス交換は、ガラス業者に依頼の連絡をしてからはじまります。近所にいつもお世話になっているガラス屋さんがある場合には、安心して依頼することができます。しかし、引っ越したばかりだったり、知っている業者がいないという状態ですと、新たに探す必要があるでしょう。
業者に依頼したら、次に見積りをしてもらいます。窓ガラスの大きさや適用しているガラスの厚みを把握するためです。
最後に、交換作業に入ります。窓枠をサッシから取り出し、古いガラスを外します。新しく強化ガラスを取り付け、窓枠をサッシに戻してから動きを確認したら完了です。
まれに不具合が見つかると、該当箇所の修理をおこなうこともあります。別途料金がかかる場合があるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
強化ガラスの交換は、普通のフロートガラスに交換するのと手順は変わりません。ただし、厚さのある強化ガラスに交換する際には、サッシや窓枠の交換をすることになるため、数日間は作業にすることになります。
強化ガラスは値段が高いですが、普通のフロートガラスとは一体どんな違いがあるのか、次の項目でお答えしています。強化ガラスへの交換を迷っているかたは参考にしてください。
どこの業者に依頼すればいいのか分からないというときには、ガラス修理お助け隊にお任せください。お電話相談の内容からお客様に適したガラス業者をご紹介できます。ガラスのことでお困りごとがありましたら、24時間365日電話相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
強化ガラスの特徴と交換するメリット
強化ガラスは、一般的に窓ガラスに使われる透明なフロートガラスと比べたら2倍近く値段が異なります。高価な強化ガラスの特徴やメリットについてまとめましたので、強化ガラスにしようかお悩みの方は検討してみてくださいね。
強化ガラスとは

強化ガラスは、窓ガラスだけでなく、グラスなどの食器類や車のフロントガラスによく使用されているガラスです。窓ガラスとしてよく使用されるフロートガラスに熱処理と冷却処理をすることで、約3~5倍ほどまで強度を上げています。
強化ガラスはその強度から見た目が気になることかと思いますが、通常のガラスとの見分けがつけられないほど自然です。衝撃に強いだけでなく、熱にも強いことから耐熱食器などにもこの強化ガラスが使われることがあります。
強化ガラスに交換するメリット
強化ガラスは、ガラス面をハンマーでたたいてもなかなか割れません。何かがガラスに飛んできたり、ガラスにぶつかったりしても割れにくいです。そのため、お子さまがおもちゃを投げたり、走りまわっても、普通のフロートガラスを設置するより安全に過ごすことが期待できます。
普通のガラスとの割れ方の違い
通常のガラスであれば、大小さまざまなサイズの破片が飛び散り、鋭利な切り口でケガをするおそれがあります。しかし、強化ガラスが割れたときには、細かく粉状に砕け散ることから、たとえ割れてしまったとしても安全な割れ方をするため、ケガのリスクが低いです。
小さなお子様のいるご家庭や、台風などの影響を受けやすい地域にお住まいの場合には、強化ガラスを窓に使用すると割れにくく、さらにケガを防ぐこともできるのです。
強化ガラスがよく使用されている場所
強化ガラスは、一番身近なものでいうと食器です。皿やフライパンのフタとしてよく使われています。車のフロントガラスも車の運転中に飛来物にも耐えられるように、強化ガラスが使用されています。
家の窓でいえば、窓、高窓、出窓によく強化ガラスが使用されます。天窓や高窓、出窓は雨風や雪の影響を受けやすいです。通常の窓にはシャッターや雨戸が付いていることが多いですが、これらの窓には設置されていないことが多いため、割れてしまうと大変危険です。しかし、強化ガラスであれば鋭利な破片が落ちてくるということがないため、安全です。
また、お子さんがいるご家庭の場合には、リビングや子ども部屋などを強化ガラスに交換することもあります。万が一割れてしまったとしても、粒子状であるため、お子様のケガを防ぐことができるのです。
強化ガラスに交換したいというときには、弊社にお任せください。全国にある加盟店から、お客様にあうお近くのガラス業者をご紹介できます。ガラス修理お助け隊では、最短10分で現場に駆け付けることも可能ですので、お気軽にご連絡ください。
強化ガラスを自分で交換することはできる?
強化ガラスの設置は、より効果的に使用するためにガラス業者に取り付けてもらうことをおすすめします。しかし、費用を抑えたいという方に向けて設置方法をご紹介しましょう。
強化ガラスの購入先

強化ガラスはガラス屋さんやガラスメーカー、インターネット通販のガラス専門店から購入することができます。自分で設置するために購入する際には、ガラスの大きさを正確に採寸してください。
採寸するときには、内寸という「サッシの内側のガラスの長さ」を測り、さらに約12ミリメートル足すと設置されているガラスの大きさになるといいます。より正確にガラスのサイズを把握するには、サッシを外し、ゴムパッキンのついた状態からガラスの実寸を測ります。
自分でガラスを交換する方法
強化ガラスをDIYで交換する手順を紹介します。強化ガラスは、種類によって厚みのあるものがありますが、元から設置していたフロートガラスと厚さが異なる場合には、取り付けられないことがあります。サッシの交換をしない場合には、設置していたガラスに近い厚さのものを取り付けましょう。
1.ガラスのサイズを測り、強化ガラスを買う
正確なガラスのサイズを測り、ガラス屋や通販などにより強化ガラスを手に入れましょう。
2.サッシから取り外す
サッシから窓枠を取り外し、窓枠のビスを外してガラスと枠を分けます。
3.強化ガラスにグレチャンを付ける
強化ガラスのまわりに、グレチャンとよばれるゴムパッキンを取り付けます。元のガラスが古い場合にはグレチャンが劣化していたり、汚れていたりする場合があるため、グレチャンも新調しましょう。
4.枠に強化ガラスを取り付ける
グレチャンを取り付けた強化ガラスを窓枠に取り付けます。ビスを締めて、外れないか確認してください。
5.サッシに戻す
サッシに戻し、スムーズに動くのか、ガラスが外れないのか確認したら完了です。
強化ガラスを交換するときの注意点
強化ガラスを交換するには、窓枠が適応していないと取り付けることができません。窓枠の対応する厚みの強化ガラスを取り付けるようにしてください。
強化ガラスは、振動や衝撃があると全体が粉砕してしまいます。作業中に壁に立てかけただけで割れてしまったり、窓枠に適切に固定されたりしていないとサッシで動かしただけで割れてしまうことがあるため、取り扱いには注意が必要です。
強化ガラスは、ガラスだけの注文でも高額となってしまうことから、失敗してしまうと大きな損害となってしまうことがあります。自分で作業することに慣れていない方や、取り扱い方法に不安があるという方は、業者に依頼しておくと安心です。
業者に依頼するとしても、取り付け費用が高い業者から、安めの価格設定の業者までさまざまです。費用相場が分からないというときには、無料で現地調査をおこなっている業者に見積りしてもらうことで、相場を知り、信頼できる業者を見つけられやすいです。強化ガラスに交換をお考えでしたら、お気軽に弊社にご相談ください。

愛車のフロントガラスにヒビが入ったとき、どのように対処するのが正解でしょうか?「すごく小さいヒビだし問題ないだろう」と考えるかもしれませんが、自動車はスピードを上げて走るので、ちょっとの傷でも風によって拡大してしまいます。そのままでは視界が悪く事故を引き起こすことも。ヒビがあると車検に通らないこともあるようです。
フロントガラスはその分厚さと丈夫さで走行中の安全を守ってくれるとても重要な存在です。だからこそ、傷がついたときにはいくら小さくてもきちんと直す必要があります。早めに対処しておけば修理費用も最小限に抑えられます。
この記事では、フロントガラスのヒビが入ったときの対処方法や予防方法などをご紹介します。「ヒビが入っちゃったけれど、対処どうしよう?」とお悩みの方は必見です!
フロントガラスにヒビが入った…
フロントガラスにヒビが入るトラブルは、案外よくあることです。どんなことが原因でヒビが入ってしまうのでしょうか?
フロントガラスは自分で補修することもできますので、高額な費用が嫌だという方は、自力でのリペアも考えてみましょう。
フロントガラスのヒビ、実は結構多いトラブルです
原因として一番多いのは「飛び石」です。車を走らせているときに小石がガラスに激突して傷がつくというもので、走行速度が速いほど石の威力も高まります。高速道路などではほんの数ミリの石でも数十センチのヒビが入ることもあるのです。
ほかには、洗車中にワイパーを倒して傷つける、ガラスが凍結して温度変化で割れてしまうといったケースもあります。
あまりに大きなヒビでなければ、自分で修理するのも可能
「走行中に石が飛んできた」「いつのまにかヒビが入っていた」といった場合も多いです。ガラスをまるまる交換するとなると数万~数十万かかってしまいますので、痛い出費です。
実は、小さなヒビなら自分でも直すことができるんです!もちろんガラスのプロに対応してもらったほうが仕上がりも安全性もよいでしょう。しかし、費用を払うのが嫌だからとヒビを放置してしまうくらいなら、自分でリペアを試すほうがはるかに安全です。
フロントガラスのヒビ、絶対に放置してはダメ!

フロントガラスのヒビ、ほんの小さいキズだからといって放置するのはNGです。そのままにしておくとヒビが拡大しますし、事故の危険性が高まってくるからです。走行中は交通事故など常に危険があるからこそ、安全第一に考えなければなりません。
また、費用の面からも早め早めの修理がおすすめです。小さいほど安く修理できますが、ヒビが拡大すれば費用は5倍、10倍に跳ね上がってしまうこともあるのです。
フロントガラスのひびを自分で修理する方法
フロントガラスのヒビは、小さなものなら自分でも直すことができます。自力でも直せる目安は、【500円玉硬貨以下のヒビ】です。
ここからはリペア用の道具を使った補修方法をご紹介します。3ステップで簡単ですので、できそうだと思ったら試してみましょう。リペアキットは通販やホームセンターでも購入可能で、比較的安価に手に入ります。
1.ヒビの周りとフロントガラス全体をきれいにする
フロントガラスを乾拭きします。水拭きするとレジン液がしっかりと密着しなくなるので、必ず乾いた布を使ってください。
傷の部分にホコリや砂が入っている場合は、針やつまようじなど先のとがったもので取り除きます。その後、ヒビの周りをマスキングテープで覆いましょう。
2.ヒビに補修液を流し込む
フロントガラスのリペア専用のUVレジン液を注入して、欠けた部分を埋め合わせます。
リペアキットの中に入っている台座をヒビの部分にセットし、台座にレジン液を入れます。レジン液が溢れてしまったときは周囲を拭きます。その後台座を外します。
3.ヒビに保護フィルムを張る
最後にレジンを注入した部分の上に保護フィルムを丁寧に貼ります。
レジンはしばらく放置しておくと、透明に硬化します。日光が当たる場所ではすぐに固まってしまいますので、夏場は日陰での作業がおすすめです。逆に真冬の低気温の日にはなかなか硬化しないので、できるだけ日差しのよい場所を選びましょう。
硬化しきったらフィルムを剥がし、余分に付着している補修液をカミソリなどを使ってキレイに取り除きます。
フロントガラスを守る方法もチェック!

補修の方法が分かっていれば次にヒビが入ったときも安心ですが、一番うれしいのはガラスにひびが入らないことですよね。
ガラスにヒビを作らない予防策を2つご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
・砂利道での走行はスピードに注意を
走るスピードを意識して、リスクを少しでも減らしましょう。
小石でもスピードが上がれば非常に危険なものと化します。山道など地面がガタガタとしていて小石が転がっているような場所では、とくにスピードに気を付けるべきです。
・カバーや解氷剤を使用する
ガラスは急な温度変化に弱いので、カバーなどを使って温度変化を極力減らすことも重要な対策です。30度、40度というような暑い夏場は車用のガラスカバーを使うとおすすめです。
冬にはガラスが凍結すると毎回熱湯をかけて溶かしているという方もいるでしょう。しかしその方法ではガラスは急な温度変化にさらされます。そのため、解氷材などの商品を使うようにしましょう。
大きなヒビが入った場合は、業者に頼ろう!
大きな障害物がガラスにぶつかったり、ほんの小さなヒビだからと放置したりすると、大きなヒビに発展してしまいます。リペアキットでの補修ができるのは500円玉ほどの大きさまでです。それ以上のサイズなら、業者に任せましょう。
業者に依頼する際には誰しもが「ちょっとでも安く、安心できる業者はどうやって選ぶべき?」という疑問を抱きます。ここからは3つの業者選びのコツを伝授します。
・複数の業者から見積りをとる
何よりも大事なのは、見積りを依頼することです。複数の業者に見積りを依頼することを「相見積り」と呼びます。相見積りをとることで業者ごとの費用の違いが明確に分かり、作業内容や費用の相場も確認することができます。
費用はヒビの状況や自動車のメーカーなどによって左右されるため、見積りなしで費用を予測するのは難しいです。業者に直接尋ねるのが一番手っ取り早くかつ正確ですので、ぜひ利用してみてください。
・見積内容は明確になっているか
見積りをもらったら、内相が詳細に書かれているかを確認しましょう。
費用がとても安くても修理方法が明記されていなかったりすると、雑な修理で済まされてしまったり、あとで追加料金を請求されてしまったりといったトラブルが起こるかもしれません。
詳細まできちんと明記された見積書は、業者が対処方法とどの程度の修理が必要なのかをしっかりと把握しているという表れとも言えます。
見積書の中で分からないこと、不可解なことがあったら、業者に質問してみるのもよいでしょう。
・実績があるかどうか
いままでどれくらいガラス交換・修理をしてきたのかという点もとても重要です。今までの経験を活かして修理をすることができる業者は、その分失敗なくキレイに補修してもらえる可能性が高いということ。とくにフロントガラスの修繕を経験したことがあるかに注目しましょう。
実績は業者のホームページに掲載された「施工例」などで確認することができます。また、実際に利用したお客様からの口コミもリアルな感想を知ることができるので見てみるとよいでしょう。
まとめ
フロントガラスにヒビが入ったとき、できるだけ早く対処することが大切だとおわかりいただけたでしょうか?ヒビがあると視界が悪く、放置するとヒビが広がってケガや事故のリスクが高まります。
リペアキットを使った簡単な修理方法もありますので、ヒビの大きさを確認して試してみましょう。さらに、運転スピードに気を付けるなどしてヒビ予防することも大切です。
ヒビが大きい場合はガラスのプロに任せる必要がありますが、依頼を決める前に安心できる業者かを見極めることが大切です。相見積りや実績を確認して、「ここならきちんと対応してくれそう」と思える業者を見つけてくださいね。

「窓のカビ掃除、早くやりたいけど効率的におこなう方法はあるのだろうか?」、いつの間にか増殖している窓のサッシやパッキンのカビ。毎日のように目にする窓のカビは、早くなんとかしたいものですよね。カビがもたらす見た目の悪さや健康被害も気になります。
窓のカビを徹底的にやっつけるためには、手順に沿っておこなうのが一番の近道です。世界からの名声を獲得する“カビバスター”の一員に、あなたもなりたいのではありませんか?今回のコラムでカビの撃退方法を学んでおけば、その道のりは一気に短くなるでしょう。
「家の窓に多くのカビが増殖していて困っている」「カビをやっつけたいけど、上手な方法が思いつかない」、そんな人はぜひ最後までご覧ください。参考になることをお約束します。
窓はカビが生えやすい?カビ発生の原因
「窓のカビ掃除をしたい」。そう考える人は多いでしょう。窓のサッシやゴムパッキンに増殖しがちなカビは、見た目の印象もよくありません。早々になんとかしたいですよね。しかし、そもそもなぜ窓周辺にはカビがたくさん増殖するのでしょうか?
カビが増殖するために必要な要素は、主に5点です。「栄養分があること」「酸素があること」「温度が適正であること」「湿度が適正であること」「増殖するための時間があること」。窓周辺は、この要素の多くを満たした環境が整っているのです。
これらのうち、初めの3点「栄養分」「酸素」「温度」に関しては、予防することが難しいといわれています。カビはプラスチックでも栄養にしますし、私たちが暮らすうえで、酸素や温度をゼロにすることはできませんよね。対処するなら、残りの2点です。
「湿度」と「時間」も、ゼロにすることは難しいですが、定期的に水分を取り除いたり、掃除をしたりすることで対処可能です。カビの胞子は目に見えないため、油断しがちですが、目に見える状態は、カビが増殖を始めているサインといわれます。
カビの増殖を防ぐためには、窓でいえば結露を除去したり、サッシにたまったホコリを取り除いたり、こまめな掃除が肝となります。カビの発生を防ぐためにはカビのとっての快適な環境を破壊すること。そのための方法を、次項から紹介していきます。
窓のカビ掃除を始める前に準備を整えよう

窓のカビを掃除する。ご存知の人もいるかと思いますが、カビは私たちの体内に侵入することで、さまざまな被害をもたらします。また、そもそもカビを直接触ったりすることが考えられない、という人も多いのではないでしょうか?
窓のカビを掃除する事前準備として、「マスク」「ゴーグル」「ゴム手袋」は用意しておきましょう。これらは“カビバスター”に入隊するために必要な、3種の神器ともいえるでしょう。カビ取り剤の中には強力なものもあります、保護のためにも必ず用意しておきましょう。
また、カビ掃除をする日は、天気のよい日を選ぶようにしてください。掃除中、掃除後は換気が必須です。これは洗剤やカビ取り剤の臭いをこもらせない意味や、カビを拭き取ったあと、室内に胞子を漂わせない意味もあります。ぜひ、覚えておいてください。
窓のカビ掃除【サッシ編】
カビ掃除をするときの手順は、大きくふたつにわかれます。「ゴミやホコリを取り除く」「カビを殺菌する」のふたつです。窓のカビを掃除していくときも、この手順に沿っておこなっていきます。サッシにせよ、ゴムパッキンにせよ、この手順は同様です。
窓のサッシを掃除するときは、まず掃除機やホウキを使って、大まかにゴミやホコリを取り除いていきます。目に見える部分をキレイにしましょう。そのあと、割り箸や歯ブラシ、綿棒などを使って汚れを落としていきます。キッチンペーパーを併用してもよいでしょう。
サッシがおおよそキレイになったら、消毒用のエタノールやカビ取り剤を使って、カビを殺菌していきます。頑固なカビが生えているところには、薬液を吹き付けたあとキッチンペーパーなどを置き、漬け置きしておきましょう。目安は15分~30分です。
それでも落ちない場合は、エタノールやカビ取り剤を吹き付ける、漬け置きをする、この工程を何回か繰り返しましょう。繰り返していくうちに、カビの根元深くまで薬液が浸透していき除去することが可能です。漬け置きしたら、都度しっかり水拭きをして終了です。
窓のカビ掃除【ゴムパッキン編】

サッシと比べて、ゴムパッキンのカビは根深いことが多いです。窓のカビを掃除するときの本丸がこちらといってもよいでしょう。“カビバスター”に入隊したばかりのあなたには、少し気が重たい任務ともいえるかもしれません。しかし、その心配は不要です。
ゴムパッキンを掃除するときには、ゴムパッキン専用のカビ取り剤が市販されていますので活用しましょう。ゴムの中に深く根付いたカビを、根本から退治するための最終兵器です。そのほか、使用するものは食器用洗剤や住宅用の中性洗剤、雑巾や新聞紙です。
まずは下準備として、床に新聞紙を敷きます。強力なカビ取り剤が床にこぼれないようにするための予防策です。新聞紙を敷いたら中性洗剤を薄めたもの、もしくは住宅用の中性洗剤を使って、ゴムパッキン周辺の汚れを取り除いていきます。雑巾は乾いたものを使用してください。
キレイに汚れを取り除いたら、カビ取り剤をゴムパッキンに吹き付けていきます。根深く色が濃い部分には、キッチンペーパーを使って漬け置きするのがよいでしょう。15分~30分ほど置いたら、水拭きして丁寧にカビを拭き取っていきます。
サッシの工程同様に、一度で取り切れない強力なカビを除去するには、カビ取り剤を吹き付け、漬け置きする工程を繰り返しておこなってください。カビが徐々に殺菌され、目に見えてゴムパッキンがキレイになっていきます。その過程は気持ちがよいですよ。
サッシもゴムパッキンも、まとめてやるのがオススメです!
サッシとゴムパッキン。これらふたつの場所を徹底的にキレイにすれば、窓のカビを退治できたといえるでしょう。ついつい先延ばしにしてしまっていた窓のカビ掃除も、いざ始めてしまえば楽しくなってくるものです。見た目も徐々にキレイになっていきます。
サッシとゴムパッキンの掃除。これらの作業は同時におこなうのがオススメです。前述したとおり、エタノールやカビ取り剤を吹き付けたあとは、漬け置きする時間が必要になります。そのあいだにもう一方の場所を掃除していくのが、もっとも効率的な方法でしょう。
準備するものや、使用する薬剤もほぼ共通のため、まとめてやってしまえば手間も圧倒的に節約できます。掃除をする際は必ずマスクとゴーグル、ゴム手袋を着用し、換気をしながらおこなうようにしてください。また、薬剤を混ぜないように注意しましょう。
窓のカビを放置してもよくないことばかり!
窓にカビが増殖することは、見た目以上におそろしい弊害(へいがい)を発生させることに繋がります。家の空気の流れ道である窓だからこその危険です。
窓のカビ掃除には見た目をキレイにするという目的のほかに、健康被害を減らすという目的もあるのです。
カビによる恐怖の健康被害
カビが生えた食べ物を口にして、下痢や腹痛が起こったという話を、耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか?それは食べ物に発生したカビ以外でも同様です。下痢や腹痛をはじめ、喘息(ぜんそく)や鼻炎など、カビが原因となる健康被害は数多いのです。
カビが原因になる悪臭
「服がなんだかカビ臭い……」、そのような経験がある人もいるのではないでしょうか?カビは悪臭の原因にもなることでも有名です。厳密にいえば、臭いを発しているのはカビではなく、カビから生まれる細菌です。しかし、カビが発生源であることは事実でしょう。
カビをエサにする微生物が増える
カビはほかの微生物のエサにもなってしまいます。ダニはその代表例でしょう。人を刺すことでかゆみを与えたり、アレルギーや皮膚炎をもたらしたりするダニの大好物はカビなのです。カビが増殖することは、ダニなどの微生物を増殖させることにもつながります。
カビの増殖が、自然になくなることはないでしょう。増殖したカビがもたらす被害は数多いです。どこかでカビを退治しなければ、これらの被害は終わることなく、悪循環を続けてしまうでしょう。カビバスターになることは、家族の健康を守ることにもなるのです。
窓にカビを発生しにくくする予防策
「窓のカビを掃除する手間が面倒くさい」、そう感じる人は多いでしょう。少しでもカビ掃除をラクにするには、記事の前半でご紹介したように“カビにとっての快適な環境を作らないこと”が大切です。カビの居心地が悪い環境を作り上げることで、窓のカビ発生を予防しましょう。
窓のカビの予防方法
具体的な方法としては、まずゴミやホコリを取り除くために、定期的に掃除をするようにしましょう。窓際にゴミやホコリがたまりやすいことは、ご存知のはずです。ゴミやホコリに水分が合わさることで、カビにとって絶好の環境が生まれてしまいます。
窓を開けて換気をおこなうことも、習慣付けておくのがよいでしょう。換気は室内の空気を入れ替える役割のほか、窓に注意を向けるキッカケにもなります。毎日とはいかなくても、定期的に換気をするクセを付ければ、カビの発生防止にも一役買うでしょう。
窓の結露を防止することも有効です
カビが増殖するために不可欠な要素のひとつである「湿気」。窓回りに湿気をもたらす大きな存在が結露であることに、異議を唱える人はいないでしょう。結露はいわばカビのとっての砂漠のオアシスです。枯れかけたカビの身体を癒す、厄介な存在といえるでしょう。
カビバスターとしては、その状況を黙って見過ごすわけにはいきません。カビがエネルギーを得る状況を、みすみす見逃すわけにはいかないでしょう。カビのオアシスである結露。簡単にできる対策と対処方法で、一網打尽にしていきましょう。
もっとも簡単な対策方法は、窓を乾拭きすることです。しかし、手間も時間もかかることは事実。ここは賢く、カビバスターの秘密道具を用いましょう。その名前は「結露防止シート」です。窓に貼るだけで、結露の発生を防ぎ、カビ増殖を防ぐことができるでしょう。
まとめ
窓のカビ掃除を始める前は正直、とても腰が重たいですよね。「明日でいいかな」「来週でいいかな」、など悪魔のささやきが聞こえてくるのは、あなただけではありません。しかし、カビを放置することは健康上の危険もともなうため、避けたほうがよいでしょう。
カビの掃除をおこなうときは必ず天気がよく、換気ができる日を選ぶようにしてください。また、マスクやゴーグル、手袋の着用は欠かせません。時間が許せば、窓のサッシとゴムパッキンを一気にまとめて片付けてしまうのがオススメです。
カビの掃除と同様に、予防策を知っておくことも重要です。そもそもカビが増殖しなければ、時間をかけて掃除する必要もありません。“カビバスター”の称号をすでにお持ちのあなたなら、予防は容易でしょう。カビがない窓で、快適な生活を送ってくださいね。

窓ガラスには、割れたときに飛び散るのを防止するための対策フィルムがあります。しかしこのフィルム、自分でキレイに貼るのがなかなか難しいという印象があるため、貼る作業は基本的に業者に任せがちです。
しかし、意外と簡単に自分でフィルムを貼ることができるんです。今回は、窓ガラスのフィルムについて解説していき、最終的に自分でフィルムを貼る方法についてもお伝えさせていただきます。
「自宅のガラスにフィルムを貼りたい」。そう考えているかたは、ぜひ参考にしてみてください。
窓ガラスにフィルムを貼ろう!オススメな理由とは?
窓ガラスにフィルムを貼ることが推奨されているのは、いくつかの理由が存在します。
窓ガラスのフィルムとはどういうもの?
窓ガラスに貼るフィルムは、一般的にはペットボトルなどに使われているポリエチレン製のシートが使われているものがほとんどです。衝撃に強いことや、伸縮性があるなどの利点からポリエチレンが選ばれています。
窓ガラスにフィルムを貼るメリット
フィルムを貼る理由は目的によってさまざまですが、窓ガラスが割れたときの飛散防止のために貼り付けているという理由がとくに多いです。近年では、地震などで窓ガラスが割れて飛び散った被害が多かったことから、こうしたフィルムへの注目も集まっています。
また、フィルムの種類によっては、窓ガラスから虫を遠ざける「防虫忌避(ぼうちゅうきひ)」の効果があるものも存在します。
窓ガラスのフィルムは多種多様!自分の家に合うものを選ぼう

窓ガラスのフィルムには、いくつかの種類があります。その代表的なものは前述したガラスの破片を防ぐものから、プライバシーを守るものまで、さまざまなものがあります。ここでは、使われることの多いガラス用のフィルムを4種類紹介します。
窓ガラスのフィルムにはどんな種類がある?
・飛散防止フィルム
台風などの自然災害で窓ガラスが割れたときに、ガラスの破片が飛び散ってしまわないように防止するフィルムです。緊急事態に備えて、貼っておくと安心でしょう。
・プライバシー保護フィルム
部屋のなかの光景を、外から見えなくする効果があるフィルムです。たとえば大きな窓が道などに面していると、外からの視線も気になりがちです。外部からの視線が気になる場合に、このフィルムを貼り付けることで外部からの視線を遮断することができます。
・防犯フィルム
空き巣対策に効果を発揮するフィルムです。空き巣の侵入経路は主にドアと窓ガラスです。この防犯フィルムを貼れば、窓が割れづらくなり防犯効果を高めることができます。
・UVカットフィルム
外からの強い太陽の光を軽減してくれるフィルムです。西日や夏場の強い紫外線が気になる場合、UVカットフィルムを貼り付けることで、紫外線を減らし、部屋の温度上昇も防ぎます。より過ごしやすい環境を作ることができるでしょう。
また、UVカットフィルムには防虫効果も期待できます。夜の虫にとって、光は大好物です。気づいたときには大量の虫が集まっていた、ということもあるでしょう。そんな虫を防ぐにもUVカットが効果的です。外に漏れる光の量を減らすことで、虫を遠ざけます。
・断熱フィルム
外の気温が屋内へ影響しづらくなる効果があるフィルムです。これにより、夏は部屋が暑くなりにくく、冬は寒くなりにくいため、部屋のなかを快適で過ごしやすい環境にすることができます。
・ミラーフィルム
ミラーフィルムを貼り付けると、窓ガラスが鏡のような状態になり、外からなかをのぞくことができない状態になります。一方で、なかからはフィルムを貼り付ける前と同じように、外を見ることができます。
・デザイン性フィルム
柄や模様が印刷されているフィルムです。部屋やインテリアに合わせて、外観のデザインを演出するために使われることが多いです。主にカフェなどのお店で使われることが多いですが、一般家庭でも、おしゃれに演出できることから使用する人もいます。
たくさんあるフィルム、選び方のポイントは?
さまざまな種類があるフィルムですが、基本的には用途に合わせて選ぶようにしましょう。
窓が割れたときの飛散防止を目的としているのか、外から見えないようにしたいのか、断熱効果を窓に持たせたいのかなど、自分が必要としている要素がなんなのか、見失わないようにすることがフィルム選びのポイントです。
【DIY】簡単!自分でも窓ガラスにフィルムは貼れます
どのフィルムを使うかを決めたら、次はフィルムを窓ガラスに貼り付けていきます。窓ガラスにフィルムを貼り付ける作業は難しそうに感じる人もいるかと思いますが、じつは素人でも手順どおりおこなえば、簡単に貼ることができます。
貼り方の手順のご紹介
ここからはフィルムの貼り方を簡単に説明していきます。事前準備として、まずは道具を用意しましょう。
用意する道具:
- フィルム
- 霧吹き
- 中性洗剤(食器洗い用などでOK)
- メジャー
- セロハンテープ
- 雑巾(ぞうきん)
- ヘラ
用意するものは以上です。これといって特殊なものは必要ありません。それでは作業を始めていきます。
・フェーズ1:下準備をしよう
まずは、窓ガラスにフィルムを貼りやすくするための、下準備をおこなっていきます。作業がしやすいように、窓付近にあるカーテンや家具を移動させておきましょう。窓付近に汚れが付く可能性もありますので、床に新聞紙を敷いておくことをおすすめします。
・フェーズ2:窓を掃除しよう
最初に石けん水を作っていきます。石けん水は霧吹きに水を入れ、中性洗剤を水に対して2~3%ほど混ぜ合わせて作ります。石けん水ができたら、窓ガラスを掃除していきます。
窓ガラスを掃除する目的は、フィルムをキレイに貼り付けるためです。ホコリや汚れが付着しているとフィルムがうまく貼り付かないため、キレイに拭き取りましょう。
先ほど作った石けん水を窓に吹き付け、ゴムベラで上から下へと、汚れをこそぐように落としていきます。
この作業を繰り返して、窓をキレイにしていきましょう。同時に窓まわりの汚れも、雑巾でキレイに拭き取っておくことをおすすめします。
・フェーズ3:フィルムを貼り付けていこう
窓掃除が終わったら、窓にフィルムを貼り付けていきます。まずは、ガラスのサイズをメジャーで測ります。そしてそのサイズに合わせてフィルムをカットしていくのですが、フィルムのサイズは4~5センチほど大きめにカットしておきましょう。
大きめにカットする理由は、ピッタリのサイズにカットしてしまうと、あとの作業で窓ガラスにフィルムを合わせるのが難しくなってしまうためです。
フィルムのカットが終わったら、石けん水で窓ガラスを全体的に濡らしていきます。水滴が垂れてくるぐらいまで、吹きかけてしまって大丈夫です。次に、カットしたフィルムを台紙から剥がし、剥がした面にも石けん水を吹きかけていきます。
この作業は、1人でおこなうのは難しいため、できれば2人でおこなうことをおすすめします。窓とフィルムの両面に石けん水を付けたら、窓の形にそってフィルムを貼り付けていきます。
・フェーズ4:仕上げていこう
窓全体にフィルムを貼り付けたら、スキマに入った余分な空気を抜いていきます。フィルム全体に石けん水を吹き付けたら、フィルムがずれないように抑えつつ、ヘラを上下左右に滑らせて空気を抜いていきます。
空気を完全に抜くことができたら、あらかじめカットしていたフィルムの余分な場所をカットしていきます。このとき、次の作業をおこないやすくするために、、ガラスのまわりとフィルムに、2センチほどのスキマをつくるようにカットしておきましょう。
最後に、窓ガラスとフィルムの間にある水を抜いてピッタリと貼り付けていく、水抜きという作業をしていきます。フィルムに軽く石けん水を吹きかけていき、ヘラを滑らせていきます。端から抜けてきた水は雑巾で拭き取りましょう。
これで窓ガラスへのフィルム貼り付けは終了です。
作業には注意をしよう
フィルムの貼り付けは、要点さえ抑えておけば素人のかたでも可能です。ただし、作業によっては1人でおこなうのが難しいものもあるするため、できれば2人でおこなうことが望ましいです。
また、窓ガラスにフィルムを貼り付ける作業には、窓を押さえて作業する場面があります。あまり強い力を加えると、作業中に誤って窓を割ってしまう危険もありますので、十分に注意して作業をおこなうようにしてください。
キレイに貼るならプロの業者へ!費用は?時間は?

自分で窓ガラスにフィルムを貼る方法を説明してきましたが、内容を確認して自分でおこなうには不安があるというかたもいるかと思います。そういった場合は、業者へ作業を依頼するのがおすすめです。
費用と作業時間について
作業時間は、施工を実際におこなう窓の大きさや数、作業者のスピードなどが影響し変わってきます。また、費用も、フィルムの種類や作業をおこなう窓の数によって変化してきます。
費用がいくらになるのか、依頼前に知りたい場合は、業者に見積りをお願いしてみてください。その際に、複数の業者から見積りをもらって比較をすれば、価格やサービス内容を簡単に比べることができます。ぜひ、作業依頼前におこなうようにしてみてください。
業者選びのポイント
せっかく作業を依頼するのなら、知識や技術のある業者を選びたいところです。そのためにはクチコミサイトなどで、業者の評判を調べる方法が効果的です。クチコミでの評判を調べ、とくに評価の高いところや、作業が丁寧なところを選ぶのがよいでしょう。
相談するときは、自分の家に合うフィルムの種類も聞いてみるようにしましょう。自分で調べることも大切ですが、専門知識のあるプロだからこその的確なアドバイスをもらうことは、大いに参考になります。
まとめ
窓ガラスに貼るフィルムには、さまざまな種類があります。窓が割れたときの飛散防止用のものや、防犯に優れたもの、UVカットができるものなど効果はさまざまです。そうしたフィルムの貼り付けは、知識がなくても手順を踏まえれば、簡単におこなうことができます。
ただし、フィルムの貼り付け作業は1人では難しい部分もありますので、2人でおこなうことをおすすめします。窓ガラスに貼り付ける作業をする際は、誤って窓を割ってしまわないように、注意を払いましょう。
もしも自分で「フィルムを貼り付けるのが難しい」と感じた場合は、業者に依頼してみるのもひとつの手です。窓ガラスにフィルムを貼り付けることで、窓のグレードアップを図り、快適な生活をおくれる環境を整えてみませんか?

家の命運をかけた“サッシ掃除”。人生で何度か訪れるこの試練に、今あなたは歩みを進めようというのですね。窓のサッシはゴミやホコリ、土やカビなどがたまりやすい場所の代名詞です。キレイ好きな人であっても、ついつい見過ごしてしまうことあるでしょう。
あまり目が付かないサッシの掃除こそ、実は気にかけたほうがよいのです。おそらくサッシの掃除にまで気が回るあなたの家は、ピカピカにキレイでしょう。その最後の試練が、サッシ掃除ではないでしょうか?そのお手伝い、当コラムが万全にさせていただきます。
窓のサッシが汚れる原因から、適切な対処方法、具体的なサッシの掃除方法までを徹底的に解説していきます。この記事を最後までお読みいただければ、あなたのサッシ掃除の知識は万全といえるでしょう。ぜひ掃除を始める前の参考として、最後までご覧ください。
窓のサッシが汚れる原因はカビ!?
窓のサッシはゴミやホコリ、土などの汚れがたまりやすい場所であることは事実です。その中でもひときわ脚光を浴びる存在は“カビ”でしょう。サッシはもちろん、ゴムパッキンなどにも増殖するカビは、適切に対処をしないと、非常に厄介なことになります。
なぜ窓のサッシにカビができるの?
家の中でも、窓は湿気がたまりやすい場所といえます。その理由は部屋の中の暖かい空気が、窓際に近づくと急激に冷やされるから。冷えた空気は水滴となって窓に付着、結露となって湿度を上昇させます。その結果として、カビが大量に増殖することになるのです。
カビが増殖を始めるときの湿度は約60%以上からです。80%以上にもなるとかなり危険な状況にあるといえるでしょう。加えて、室内はカビにとっても最適な温度帯です。湿度と温度を兼ね備えた窓周りはカビにとっての楽園。増殖してしまうのも、もっともでしょう。
カビの掃除は、重曹とクエン酸が効果的!
サッシにはびこる多くのカビ、その存在はできれば放置しておきたくないところでしょう。カビは放置をすると、多くの健康被害をもたらします。除去をするには重曹とクエン酸を用いるのがもっとも手軽、かつ容易にできる方法のひとつといえるでしょう。
まず、水100mlとクエン酸小さじ1/2をスプレーボトルに混ぜ込みます。その“クエン酸スプレー”をカビに直接噴射、その上から重曹を振りかけます。泡が出ますがそのままで大丈夫です。30分ほど放置をしたら、水拭きと乾拭きをして、しっかりと乾燥させてください。
【基本的編】サッシお掃除4ステップ

さて、前章では非常に厄介な、窓に増殖するカビの対処方法を見てきました。この章では窓のサッシ掃除の方法を見ていきましょう。この記事の本題ともいえます。準備するものと、それぞれの手順を確認し、これから始めるサッシ掃除の用意を整えてみてください。
準備するもの
【ステップ1】窓と網戸を外す
まず、窓と網戸をサッシから外していきましょう。方法がわからないときは、説明書を参照してみてください。また、窓と網戸を外すのは結構な重労働となります。とくに戻すときは持ち上げる必要もあるので、2人でおこなうのが確実といえるでしょう。
とはいえ、窓や網戸は必ずしも外さなければいけないわけではありません。大切なのは無理をしないことです。外したほうが掃除の完成度は高くなりますが、絶対条件ではないことは覚えておいてください。時間があれば併せて窓の掃除をしてしまうのもよいでしょう。
【ステップ2】乾いたブラシでホコリを取り除く
サッシの掃除でやりがちな間違いが、“いきなり水を使用してしまうこと”です。固まったゴミには水分が効果的ですが、比較的軽いゴミやホコリは、乾燥した状態のほうが圧倒的に処理がラクです。まずはブラシやつまようじを用いて、ゴミやホコリを除去しましょう。
固くこびりついてしまったゴミやホコリがあれば、少し水をかけてふやかすようにしてください。また、最近では100円ショップなどで小さなブラシが販売されています。作業がとてもはかどるので、余裕があれば用意しておくのもアリでしょう。
【ステップ3】水のついたブラシで残った汚れを取り除く
大まかにゴミやホコリを取り除いたら、ここから本格的な掃除の始まりです。使用するのは基本的に水と歯ブラシ。サッシの汚れの多くは土などの汚れのため、洗剤なしの水だけでも十分な効果が見込めます。水を少量ずつまいて、こまめに歯ブラシでこすりましょう。
非常に手ごわい汚れや、油汚れが見受けられる場合は、洗剤を用いるのもよいでしょう。しかし、あまりに多い洗剤は処理が大変になるので、控えたほうが無難ともいえます。
【ステップ4】水で流して拭き取る
サッシ全体の掃除が終了したら、水を少しづつ流してすすいでいきます。一気に流さないのは、サッシから水が溢れて大洪水を引き起こさないようにするための配慮です。すすぎが終了したら、乾いた布を使ってサッシを拭き上げましょう。乾かしたら掃除は終了です。
サッシの掃除は、基本的に上記の手順に沿っておこなっていきます。準備するものも少ないため、掃除をすることも難しくはないでしょう。とはいえ、じつはこの方法以外にも、画期的な秘密の方法があります。その全貌を(ぜんぼう)を、次章で解説していきます。
【簡単ラクチン】サッシ掃除はスポンジを使えばあっという間に解決!
“サッシ掃除をラクにやりたい”、そんな全人類の望みを叶えてくれる魔法のアイテムが“スポンジ”です。それも特殊なものは必要なく、一般的なスポンジで十分に通用します。
スポンジを用意したら、まずは切り込みを縦横に入れていきます。見事にカットしたマンゴーの姿を、見たことがあるでしょうか?切り込みは、あの偉大な姿に似ています。切り込みを入れたスポンジと、水をためたバケツ、そして乾拭き用の雑巾を用意しましょう。
この後の手順に難しいものはありません。サッシにスポンジを当てながら、全体を掃除していくだけです。切り込みがサッシの形状にはまるため、スイスイと作業を進めることができるでしょう。時折バケツにためた水で、スポンジの汚れを落としてあげてください。
全体を掃除することができたら、最後に雑巾で乾拭きをして作業は終了です。重要なのは、切り込みを入れたスポンジを用意することです。スポンジはまさしく、サッシ掃除界のプリンスといえるでしょう。どんな状況もこのスポンジがあれば、おそるるに足らずです。
【番外編】スポンジ以外にもオススメしたい!4種類のサッシ掃除アイテム!

サッシ掃除界には、スポンジだけに王者は譲れない……と、さまざまなアイテムたちが登場してきています。ここではその中から人気を集める4種類のアイテムを紹介。どのアイテムも素通りは厳禁です。サッシ掃除を快適な作業へと、生まれ変わらせてくれますよ。
ペットボトル
ペットボトルに装着する、俗にいう“アタッチメント”がこちらです。ペットボトルの先端に付けるタイプのブラシや、加圧式のスプレーなど、さまざまな種類のアイテムが揃っています。基盤はペットボトルで使用しやすいため、手軽に購入することもできるでしょう。
木工用ボンド
サッシの隅にこびりついた固く頑固な汚れ。その除去には木工用ボンドが、非常にお役に立つでしょう。汚れの上から木工用ボンドを乗せてしばらく放置、ボンドを固めます。ボンドが固まったら、そのままはがしてゴミ箱へ。なんとも手軽な方法といえますね。
重曹
サッシの掃除で重曹を用いるのは、カビに対処するときです。使用するのは重曹とクエン酸。このふたつを1:1の割合で混ぜましょう。混ぜたペーストをカビの上に直接乗せ、そこに霧吹きで水を吹きかけます。30分ほど放置したら布などで拭き取って、掃除終了です。
片栗粉
片栗粉を使用するのは重曹と同様に、カビの対処をするときです。こちらは塩素系の漂白剤を使用する方法で、より頑固なカビを除去したいときに選ぶ方法といえるでしょう。用意するものは“大さじ1杯の片栗粉”と“同量の塩素系漂白剤”、それに紙コップです。
ふたつの材料を紙コップに投入、混ぜてペースト状にします。作成したペーストをカビの上に置き、5分ほど放置しましょう。時間が経過したら、雑巾などでキレイに拭き取ります。片栗粉と塩素系漂白剤が根元まで浸透し、カビを根本から除去することができるでしょう。
上記の4点はサッシ掃除においては“救世主”とも呼ぶべき存在です。効果的に使用すれば、窓サッシの掃除を快適に、かつスムーズに進めることができるでしょう。とくに入手が難しいものもないので、ぜひとも活用してみてください。劇的に、お役に立ちますよ。
窓のサッシを掃除するならココに気をつけて!
窓のサッシ掃除は、方法によっては注意するべき点がいくつかあります。これらの注意点を知らずに始めてしまうと、困った事態になる可能性もあります。ここでは3つの注意点を解説、先に読んで内容を覚えておき、快適にサッシ掃除を進めてみてください。
無理をしない
主に窓や網戸を取り外す段階において、無理は禁物です。ときに重たいものもある窓や網戸、無理をして外してしまうと、腰などを痛めてしまうことも考えられます。どうしても外したいときは、一人で作業をおこなうのではなく、二人でおこなうようにしましょう。
窓と網戸の説明書を確認する
窓と網戸を外すことと、再びつけることはいわば別問題です。取り付けるときに困ってしまうこともあるでしょう。不要なトラブルを解消するためには、事前に説明書などを読み込んでおき、適切に対処ができるように、知識を準備しておくことが必要でしょう。
洗剤を放置しない
たとえば、塩素系漂白剤を使用して掃除をおこなったときなどに該当します。短時間で効果が望めるものは、それだけ強力な成分が含まれています。長時間の放置は控えましょう。思わぬところで、サッシやゴムパッキンの劣化につながってしまいます。
頑固な汚れはプロの掃除が一番?もしかすると交換のタイミングかも!
サッシの掃除やゴムパッキンの清掃など、窓周りのメンテナンスは意外と後回しにしてしまいがちです。もし、自分で掃除をするのが面倒と感じるようであれば、ハウスクリーニングなどの業者に、掃除依頼をするのもよいでしょう。徹底的にキレイにしてくれます。
また、それでもなかなかキレイにならない、もしくは家を建ててから長いあいだ、窓やサッシの新調をしていないという人は、この機会に新しくするのもよいでしょう。頑固な汚れやカビは、徹底的に掃除をしても、除去しきれないことが多々あります。
もし、窓サッシの新調を検討するのであれば、“相見積り”をとることが、非常にお役に立つでしょう。相見積りとはいくつかの業者へ見積りを依頼し、その内容を比較する、というものです。最安値で作業をおこなってくれる業者や、費用相場を知ることも可能ですよ。
まとめ
なかなか手が出ない窓サッシの掃除、今回の記事を参考に、ぜひとも始めてみてください。サッシの積み重なったゴミやホコリはもちろんのこと、目にするのも嫌なカビなども、キレイに除去することができるでしょう。事前準備をしっかりとして、掃除に挑みましょう。
窓のサッシを掃除する方法は、基本的には窓を外してゴミやホコリを除き、水拭きをして乾かす、というものです。使用するのは使い古した歯ブラシや布切れでも十分でしょう。もし、スポンジが手元にあれば、作業が圧倒的にはかどるので、使用をオススメします。
サッシ掃除で窓や網戸を外すときは、無理はしないように、可能であれば二人でおこなうのがベストでしょう。面倒と感じるのであれば、掃除、もしくはサッシ交換をしてしまうのもアリかもしれません。窓周りをキレイにして、快適な住環境を手に入れてくださいね。

外の景色を見るためにあるガラス。建物に至ってはガラスが使われていない建物はごく稀です。それほどまでにガラスは私たちの生活と密接な関係にあります。
ガラスの種類といってもたくさんありますので、すべてを細かくご紹介するのは難しいです。今回はそんなガラスの中でも「アクリルガラス」にスポットを当ててご紹介していきます。
ガラスとアクリルガラスの違いや、アクリルガラスに似たガラスについて。またアクリルガラス以外のガラスの種類についてもいくつかご紹介させていただいてます。
このコラムを読めば、アクリルガラスについてはもちろん、ガラスについての知識もつくはずです。ガラスに対して詳しくなり、適材適所なガラス選びをしていきましょう。
ガラスの特徴とメリット・デメリット
まず最初に、ガラスというのはどのようなものなのか。というところから説明いたします。ガラスのことを知れば、アクリルガラスについてもより興味が湧き、知識も深まっていくでしょう。
ガラスとは
ガラスの生い立ちは古く、古代の頃から黒曜石として狩猟などで役に立っていました。そんなガラスは、電気を通さない素材であり、酸化して錆びるということもありません。そういった意味では、他の材質とは違う特徴がたくさんあります。そんなガラスの特徴について、メリットとデメリットの点を見ながら説明していきます。
ここがすごい!ガラスのメリット
ガラスのメリットはなんといっても、無色透明なので、外や中の景色がしっかり見えるところでしょう。また種類によっては、水槽などにも使われており、ガラスがなければ見られない光景も見ることができます。
またガラスは高温の熱を与えると変形する性質があり、加工がしやすいです。この変形する性質のおかげで、ガラス細工というものが生まれました。また加工の点では着色などのも可能です。
ステンドグラスが代表的でガラスの着色を使って芸術を楽しんでいた時代もあったほど、生活に欠かせない存在になっています。
ガラスのデメリット
ガラスは衝撃に弱いです。落としたりなどの衝撃を与えるだけで、割れてしまいます。またガラスの破片はとても鋭利です。扱いかたを間違えてしまうと、ケガをしてしまいます。ガラスを取り扱うときは丁寧な扱いが必要です。
アクリルガラスの特徴とメリット・デメリット

アクリルガラスとガラスは名前こそ似ていますが、実際は違う点が多いです。そんなアクリルガラスについてご紹介していきます。
アクリルガラスとは
まず最初にアクリルについて説明します。アクリルとはアクリル樹脂を使った製品です。ガラスとは違う性質の素材からできており、無色透明の色は似ているのですがそれ以外は違いが多いです。
アクリルガラスはこのアクリル樹脂で生成されたガラスになります。見た目や質感はガラスに近いのですが、性質はガラスとは全く異なるのです。
アクリルガラスのメリットとは
アクリルガラスはアクリル樹脂でできていますので、アクリルの特徴を引き継いだガラスになります。そしてアクリルのメリットは以下の部分があります。
- ガラスと比べると非常に軽い
- 耐久性が強く簡単に割れたりしない
- ガラスよりも透明度が高い
- 熱処理や接着の加工がしやすい
アクリル自身はプラスチックの一種になります。プラスチックのような特徴と、ガラスならではの特徴の両方を兼ね備えたのがアクリルガラスなのです。
アクリルガラスのデメリットとは
プラスチックのように硬く、ガラスのように透明なアクリルガラスですが、当然デメリットもあります。
- 割れにくいが、とてもキズがつきやすい
- 静電気を帯びるため、ホコリがつきやすい
- 耐熱温度が約80℃とガラスに比べ熱に弱い
丈夫だけどキズがつきやすく、ホコリもつきやすい。また耐熱温度もそこまで高くないので、ガラスより透明度は高いのですが、窓には向いていない性質になっています。
アクリルガラスによく似たポリカーボネートとは?
アクリルに似た存在でポリカーボネートという素材があります。このポリカーボネートもプラスチックの一種になるので、おおまかな性質はアクリルガラスとよく似ています。ただいうなれば兄弟のような関係で、細かい特徴はそれぞれ異なります。ここではポリカーボネートについての特徴やアクリルガラスとの違いについて説明していきます。
ポリカーボネートとは
ポリカーボネートはポリカーボネート樹脂と呼ばれる素材から作られています。そんなポリカーボネートの特徴は以下の通りです。
- プラスチックの種類の中で一番衝撃に強い
- ガラスと同じくらいの透明度
- 吸水性は低く、水をはじく
- 自己消化性という火に強い性質を持つ
- 気候の変化に強い
- 加工は難しく、変形しにくい
- キズがつきやすい
- アルカリ性に弱い
耐久性がとても強く、ガラスと同じくらいの透明度というのがポリカ―ボネートのメリットです。またキズつきやすく、変形しづらい。また界面活性剤に弱くひび割れや変形してしまうのがデメリットです。
アクリルガラスとポリカーボネートの違い
アクリルガラスは、ポリカーボネートよりも加工がしやすく透明度が高いのが特徴です。そしてポリカーボネートはアクリルガラスより衝撃や気候、火への耐性がとても高いです。
透き通るような透明度を求められる場合には、アクリルガラスが使われます。またある程度の透明度が必要で、絶対的な耐久性が欲しいというところにポリカーボネートが使われています。主にカメラのレンズ部分に使われているのがポリカーボネートです。
アクリルガラスはさまざまな場所で活躍しています

アクリルガラスの透明度と加工のしやすさ。そして低い温度への耐性を考えて、水族館の水槽などに使われています。
その他にはボールペンやコップといった日用品からテールランプなどの照明器具。他にも携帯電話や浴槽やトイレなどの水回り関係にも使われています。アクリルガラスは私たちの生活のいたるところで活用されています。
ガラスは多種多様。アクリルガラス以外のものについて
ここまではアクリルガラスを中心に説明していましたが、ガラスという素材にはたくさんの種類があります。ここからはそんなガラスの種類と簡単な特徴についてご紹介していきます。
●フロートガラス
一般的な1枚ガラスをフロートガラスといいます。窓などに使われています。
●網入りガラス
ガラスの中にワイヤーを網状に入れ、ガラスの強度を上げます。ガラスが割れたとき、飛び散りにくくなる性質があります。ぶつかりやすい場所の窓などに使われます。
●型板ガラス
ガラスの奥が見えにくくなるように加工してあるガラスです。片面がデコボコしていて反対面はツルツルな触感です。お風呂や玄関などに使われます。
●強化ガラス
厚みのあるガラスです。厚みがある分強度も上がっています。一般的にガラステーブルに使われているガラスが強化ガラスになります。
●複層ガラス
2枚のガラスを合わせているのですが、ガラスの間にわずかな隙間があります。ガラスの強度が上がるだけでなく、断熱効果と結露を防止する高価もあります。窓ガラスに特化したガラスです。
●合わせガラス
複数のガラスを貼り合わせています。またガラスとガラスの間に特殊なフィルムをはさんでおり、強度が高く、割れたときガラスが散らずヒビが入るような状態になります。車のフロントガラスや防犯用のガラスに使われます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ガラスにはたくさんの種類があり、それぞれ特徴も違います。その特徴を活かして、私たちの生活で適材適所に設置されています。
そんなガラスも耐久性に優れていても、いつかは割れたり破損したりしてしまいます。またガラスの種類によっては、拭いてもとれないような汚れが残ってしまうこともあります。そういった場合はガラス自体の寿命がきていることになります。
ガラスに寿命が来てしまったならば、ガラス業者を呼んでガラスの交換をしてもらいましょう。ガラス業者はガラスに関しての知識が豊富なプロです。交換するガラス部分にはどんな種類のガラスが相性がよいのか相談してみるのもよいかもしれませんね。

ガラスといえば割れやすいものですよね。割れたガラスは刃物のように、私たちの体を傷つけてしまう危険なものになってしまいます。そのため、人がよく利用するような場所は普通のガラスよりも割れにくい「強化ガラス」が使われていることが多いです。
お住まいの家の窓を、強化ガラスにしている人もいらっしゃるかもしれません。しかし、強化ガラスだからといって絶対に安全かといえば、じつはそうではありません。今回は強化ガラスの割れ方や割れてしまう原因に加え、ガラス割れの対策をご紹介いたします!
強化ガラスの割れ方の特徴
割れなくて安全なはずの強化ガラスが、割れてしまうことなんてあるのでしょうか?そもそも「絶対に割れないガラス」などというものは、残念ながら世の中には存在しません。強化ガラスも割れるときはあるのです。
ただし、強化ガラスは割れ方に特徴があり、一般的に使われているフロートガラスよりも安全性に配慮した割れ方をします。強化ガラスは割れたときに肌を切るような大きな破片が飛び散ることはなく、尖っていない小さな破片が狭い範囲に落ちるため、危険が少なくなっています。
一般的なガラスは放射状に大きく割れて、破片はナイフのように尖っているため、ちょっと触っただけで簡単に肌を切ってケガをしてしまいます。また、窓枠にも大きな破片が残ることが多いので交換にも危険が伴うでしょう。
一方強化ガラスは窓枠に破片を残すことなく、割れるときはガラス全体が粉砕する構造になっているため、後の交換処理も比較的簡単にできるようになっています。強化ガラスは絶対に割れないガラスではありませんが、安全性に最大限配慮しているガラスなのです。
ヒビを放置すると危険!
しかし強化ガラスは小さな傷が生じることにより、突然割れてしまうことがあります。なぜなら、強化ガラスはガラスの表面と内部に異なる力が等しく加わっているため、傷が生じることにより、その力のバランスが崩れてしまうからです。
また強化ガラスは傷が生じたと同時に割れるのではなく、傷が徐々に広範囲へ広がることで突然割れることが多いです。ガラスに傷やヒビが生じている際は、突然ガラスが割れることによるケガのリスクに備え、放置はせず早めに交換することをおすすめします。
「割れない」イメージの強化ガラス、その構造とは

一般的なガラスよりも割れにくい強化ガラスが割れてしまうときというのは、どういうときなのでしょうか。強化ガラスは耐久性を高める構造をしていますが、それによって新たな弱点を生み出しているガラスでもあるのです。
強化ガラスは一般的なフロートガラスに、追加の処理を加えることで製造されています。フロートガラスを約700度で熱したのち、冷気を一気に吹き付けて表面を瞬時に冷却することで強化ガラスはできあがります。
この加熱・冷却の処理によって、ガラス表面には内側へ圧縮しようとする力が、内部ではバランスを保つために外側へ膨張しようとする力が同時に働いて2つの層が生まれます。簡単にいえば、強化ガラスはバランスのいい2重構造になっていることで、高い耐久性を実現しているのです。
強化ガラスの弱点を知っておこう
加熱・冷却処理によって2重構造を生み出し、耐久性を高めている強化ガラスですが、この処理によって通常のガラスにはない新たな弱点も生み出してしまっています。
・一点の衝撃に弱い
強化ガラスは衝撃を全体に分散することに長けているため、一般的なガラスよりも面に対する衝撃には強く、滅多なことで割れることはありません。しかし反面、一点に集中した衝撃には非常に弱くできています。そのため防犯対策として活用しても、ハンマーやバールなどで割られてしまうおそれが高いため、防犯には不向きです。
石や自然災害時に飛散したものがぶつかるのを防ぐには、シャッターや雨戸を取り付けるのがおすすめです。そのほかにも、格子(木や鉄などを組んだもの)を取り付ける方法もあります。
「雨戸などを新たに設置するのは難しい」「ガラス自体を防犯性の高いものに交換したい」といった際は、防犯ガラスに交換することをおすすめします。防犯ガラスの特徴や交換時の費用相場など、詳しく知りたい際はこちらをごらんください。
・急な温度変化に弱い
ほかには一般的なガラスと同様に、急な温度変化に弱い特徴があります。とくに、冬になると暖房機器を使用することが増えるため、室内外の温度差によって“結露”が生じやすくなるので気をつけましょう。
結露が増えると窓のサッシ部分に水が溜まっていきます。サッシ部分の多くはアルミなどでできているため、水によって温度が下がりやすいのに対し、ガラスの表面は太陽によって温められることで、表面温度が上がります。それによりサッシ部分とガラス表面に温度差が生じて、ガラスが割れやすくなるのです。
また、ガラスは熱を吸収することで熱せられた部分が膨張するのに対して、サッシ部分は温度が上がらないため、膨張しません。ガラスが膨張すると、ガラスに引張応力といった力が加わるため割れる原因にもなります。
ガラスに加わる力については次に解説する【「圧縮応力層」に強い衝撃が加わったケース】(ページ内リンク)をごらんください。強化ガラスが割れるこれらの症状を“熱割れ”と呼びます。
ガラスのサッシ部分に結露を発見したら、こまめにタオルなどで拭き取って熱割れを防止しましょう。また結露の発生を防ぐには、強化ガラスの近くに暖房器具を配置しないようにすることも大切です。
強化ガラスに交換をお考えの方は、弊社にお任せください
強化ガラスには以上で説明したとおり、さまざまなメリットやデメリットがあります。強化ガラスについてより詳しく知りたい方や、交換をお考えの方がいましたら、お気軽に弊社にご相談ください。
強化ガラスに交換する場合、交換時にかかる値段が気になる方もいることでしょう。以下のサイトでは、強化ガラスの本体価格や、交換作業でかかる費用について解説していますので、ぜひ合わせてごらんください。
強化ガラスでも割れてしまう原因
強化ガラスを強化している表面と内部の層ですが、皮肉なことにこの2つの層の圧縮と膨張の力が強化ガラスの割れる原因になるケースも多いです。この章では強化ガラスの割れ方をこの力の観点からもう少し詳しく解説していきます。
「圧縮応力層」に強い衝撃が加わったケース
強化ガラスが冷却された際に生まれる、内部に圧縮しようとする表面層のことを“圧縮応力層(あっしゅくおうりょくそう)”といいます。外部からの衝撃に強い圧縮応力層に傷を受けただけでは、強化ガラスが割れることはありません。
強化ガラスが割れるのは、圧縮応力層を貫いて内部の“引張応力層(ひっぱりおうりょくそう)”に衝撃が伝わったときです。引張応力層まで衝撃が伝わると、一瞬で2つの応力のバランスが崩れてしまい、結果粉々に割れてしまうことになるのです。
小さな一点に衝撃を受けた場合、引張応力層まで衝撃が伝わってしまう場合が多く、小さな小石がぶつかっただけで割れてしまうケースもあります。また、表面に傷が蓄積されることで、ある日突然内部の層があらわになって割れてしまうケースもあるようです。
ガラスに石がぶつかるのを防ぐには、先ほど紹介した雨戸やシャッターの設置をおすすめします。強化ガラスの表面に生じる小さな傷は、ガラスにぶつかるほかに拭き掃除などをする際にできやすいです。そのため強化ガラスの拭き掃除をおこなう際は、クレンザーなどの研磨剤は使用せずに雑巾やタオルを使うとよいでしょう。
ガラスの品質が悪く、不純物が含まれていたケース
製造時の管理不足で、割れる原因が生み出されてしまうこともあります。ガラス内部には時折“硫化ニッケル”が含まれることがあります。硫化ニッケルは原料由来の不純物です。
この不純物も含めた状態で、そのまま2重構造の力のバランスが保たれるように製造してしまうと、後に温度変化によって不純物が膨張することがあります。この膨張した不純物が内部から応力層のバランスを崩してしまい、自然破損を起こしてしまうことがあります。
製造時に不純物(硫化ニッケル)が混入しているのかを確認するには、“ヒートソーク処理(ソーク処理)”が不可欠です。
ヒートソーク処理とは、製造した強化ガラスを約300度で熱することで不純物が膨張し、ガラスを破壊させる方法を指します。多くのガラス製造会社では、ヒートソーク処理が施されているため滅多に不純物によって割れることはありません。
仮にガラスに不純物が含まれていたことによって割れた場合、メーカーや購入した店舗に問い合わせをすることで、無償で交換してもらえることがあるので、一度相談をしてみるとよいでしょう。
強化ガラスの割れ方が不安?割れや飛び散り対策法

強化ガラスが割れ方に配慮した安全なガラスといっても、割れたときにケガをする危険がまったくないわけではありません。できることなら割らずに使い続けたいものですが、何か対策はできないのでしょうか。
防犯フィルムが強化ガラスの割れ防止に有効!
不審者が窓から侵入するのを防ぐ防犯フィルムですが、単純に窓の割れ防止として活用するのも有効といわれています。
防犯フィルムは適当なものを選ぶのはおすすめできません。できれば確実に防犯効果があると認められた製品が取得できる“CP認定”がされているフィルムを選ぶと、割れ防止にも防犯にも効果的でしょう。
飛散防止シートも飛び散り防止できて安心
ガラスが割れてしまったときに、破片が周囲に飛散するのも非常に危険なことです。ホームセンターなどで販売されている“飛散防止シート(フィルム)”を貼れば、割れたガラスが飛び散るのを防ぐことができます。
ただし、飛散防止シートはあくまでガラスの飛び散りを防ぐものです。ガラス割れ自体を防止するわけではないので、そこは勘違いしないようにしましょう。
強化ガラスよりも強い、合わせガラスに取り替える
フィルムやシートを貼るだけでは信用できない!という方は、強化ガラスよりもさらに強い強度を誇る“合わせガラス”に交換してみるのをおすすめします。
2枚以上のガラスを接着した合わせガラスは、強化ガラスのように一点の衝撃でもすぐに割れることはなく、万が一割れたときにも、破片が落ちにくい構造になっています。
小さなお子様に留守番をさせてしまうことが多いご家庭にも、防犯用としても非常におすすめのガラスです。
まとめ
強化ガラスは一般的なガラスよりも耐久性が高く安全なガラスですが、条件によっては簡単に割れてしまうことがあります。
強化ガラスは小石がぶつかったりバールで叩かれたりなどの、一点に集中した衝撃には非常に弱い構造になっています。また長年の傷が蓄積したり、製造時にまぎれた不純物によって、自然破損してしまったりする場合があります。
防犯フィルムや飛散防止シートを取り付けることで、手軽に強化ガラスの安全性を高めることができます。より確実な安全性を求めるなら、強化ガラスよりもさらに強度が強い「合わせガラス」を検討してみるのもいいでしょう。
弊社は強化ガラスや防犯ガラスなど、さまざまなガラスの交換に対応する業者をご紹介しております。また、交換をおこなう前に、ガラスの厚みや寸法、種類を確認し、実際に依頼した際にかかる費用の見積りを無料でご提示させていただきます。
年中無休で電話相談に対応いたしますので、依頼時に費用や気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。